 PC関連
PC関連 パスワード管理『KeePass Password Safe』…日本語化とUSBメモリで運用!
USBメモリに入れて利用することで、PCを限定せずに利用することが可能です。ポータブル版をダウンロードし解凍後、そのままUSBメモリに入れるだけ。また、日本語化については、ランゲージファイルを、KeePassと同じフォルダーへコピーペーストすれば完了。
 PC関連
PC関連 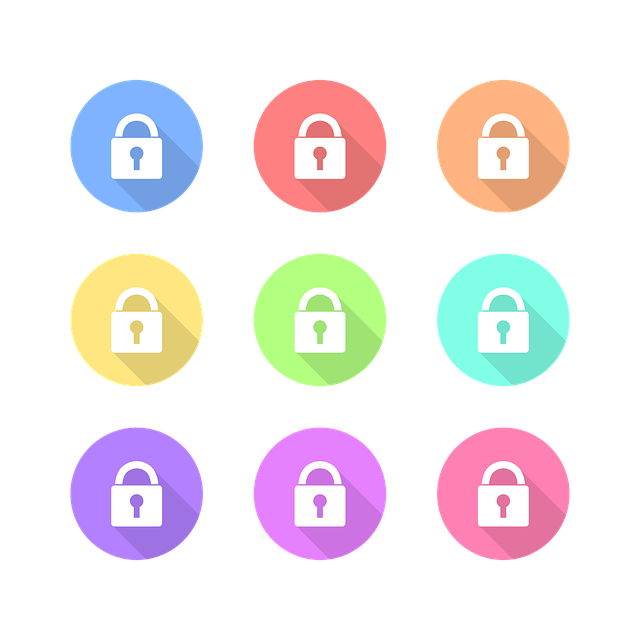 PC関連
PC関連 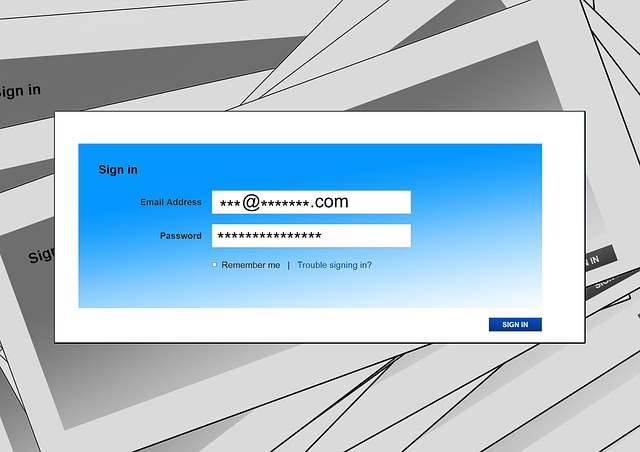 ちょっとした知識
ちょっとした知識  ちょっとした知識
ちょっとした知識 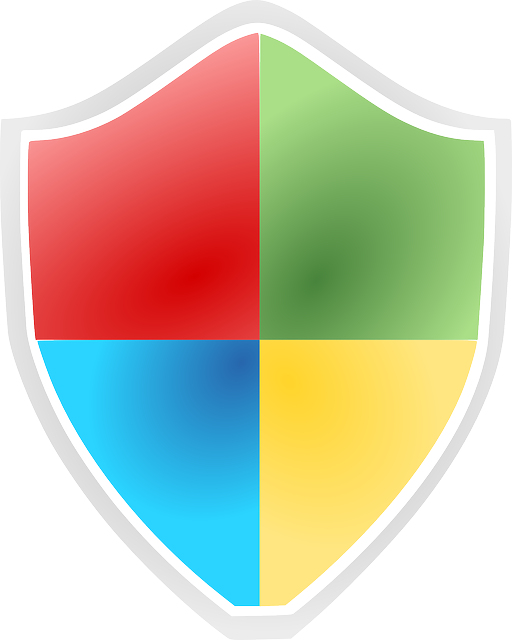 Windows関連
Windows関連  ちょっとした知識
ちょっとした知識  ちょっとした知識
ちょっとした知識  ちょっとした知識
ちょっとした知識 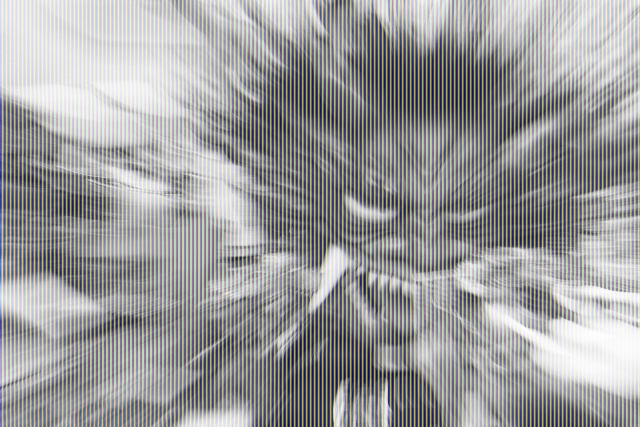 ちょっとした知識
ちょっとした知識 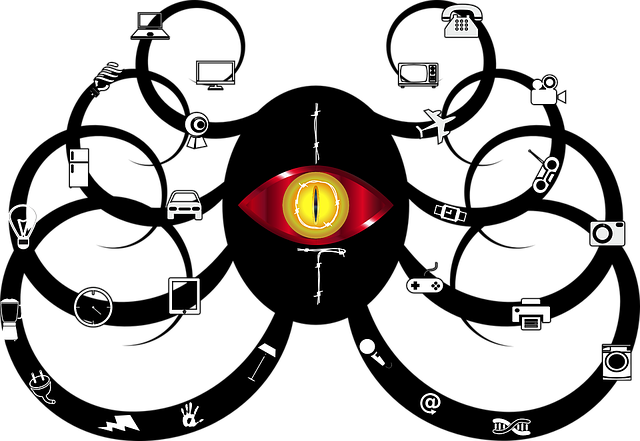 ちょっとした知識
ちょっとした知識